学資保険とは?特徴とメリット・デメリット
まず初めに…
学資保険とは、子どもの教育資金を
準備するための保険商品です。
毎月定額を積み立てて、契約満期時に
まとまったお金を受け取れる仕組みになっています。
- メリット↓
- 返戻率がある程度読めるため、大きなリスクがない
- 親に万が一があった場合、保険料が免除されることがある
- デメリット↓
- インフレに弱く、利回りが低い(返戻率は100~105%程度が多い)
- 途中解約すると元本割れするリスクが高い
新NISAとは?積立投資のメリット・デメリット
新NISAは、株式や投資信託を非課税で運用できる制度です。
2024年からは生涯非課税投資枠が
最大1800万円
になり、長期投資に最適な環境が整いました。
- メリット↓
- 運用益や配当が非課税(通常20%かかる税金がゼロ)
- 長期積立で複利効果を最大限に活かせる
- 長期で見ればほぼほぼ元本割れはゼロに近い
- 教育資金だけでなく老後資金にも使える
- デメリット↓
- 元本保証がない(相場によってはマイナスもあり得る)
- 短期での値動きに不安を感じやすい
学資保険とNISAを比較|返戻率と運用効率
- 学資保険:返戻率はせいぜい105%前後 → 年利換算で1%にも満たない
- NISA(投資信託):平均リターンはインデックス投資の場合、年5%は期待できる
例えば、毎月1万円を18年間積み立てた場合:
- 学資保険:約220万円(元本216万円+数万円の上乗せ程度)
- NISAで年利5%運用:約350万円(元本216万円+130万円以上の運用益)
この差は歴然で、長期的に見ればNISAの方が圧倒的に教育資金を効率的に増やせます。
※お子さんの年齢が10歳を超えていると長期運用がなかなか難しいので教育費としての運用はリスクあります。
子育て世代におすすめはどっち?
- 「絶対に元本を割りたくない」→ 学資保険
- 「長期で資産を増やしたい」→ NISA
特に教育費は15~18年後に必要になるため、
十分な運用期間があります。
リスクを取ってでも資産を増やしたい家庭には、
NISAでインデックス投資が圧倒的に有利です!
実際自分も教育費はNISAで貯めていきます!!
まとめ|学資保険よりNISAで教育費+老後資金を両立
言うなれば、学資保険は「守り」、NISAは「攻め」。
ただし教育費は数百万円単位で必要になるため、
NISAで積み立てつつ、
万が一に備えて掛け捨て保険で
リスクヘッジするのが現実的な選択肢です。
子育て世代は教育費と老後資金の両立が大きな課題。
NISAを上手に使えば、教育費を準備しながら
老後資金も並行して積み上げられるというメリットがあります。
https://susan-blog.com/%e8%b2%af%e9%87%91%e3%82%bc%e3%83%ad%ef%bc%81%e5%85%90%e7%ab%a5%e6%89%8b%e5%bd%93%e3%82%92%e4%b8%b8%e3%81%94%e3%81%a8nisa%e3%81%ab%e5%9b%9e%e3%81%99%e7%90%86%e7%94%b1/
年利別|児童手当を投資に回したらどうなる?シミュレーションしてみた ↓

ページが見つかりませんでした -
教育費はいくら必要?子育て世代が知っておきたいリアルな数字 ↓
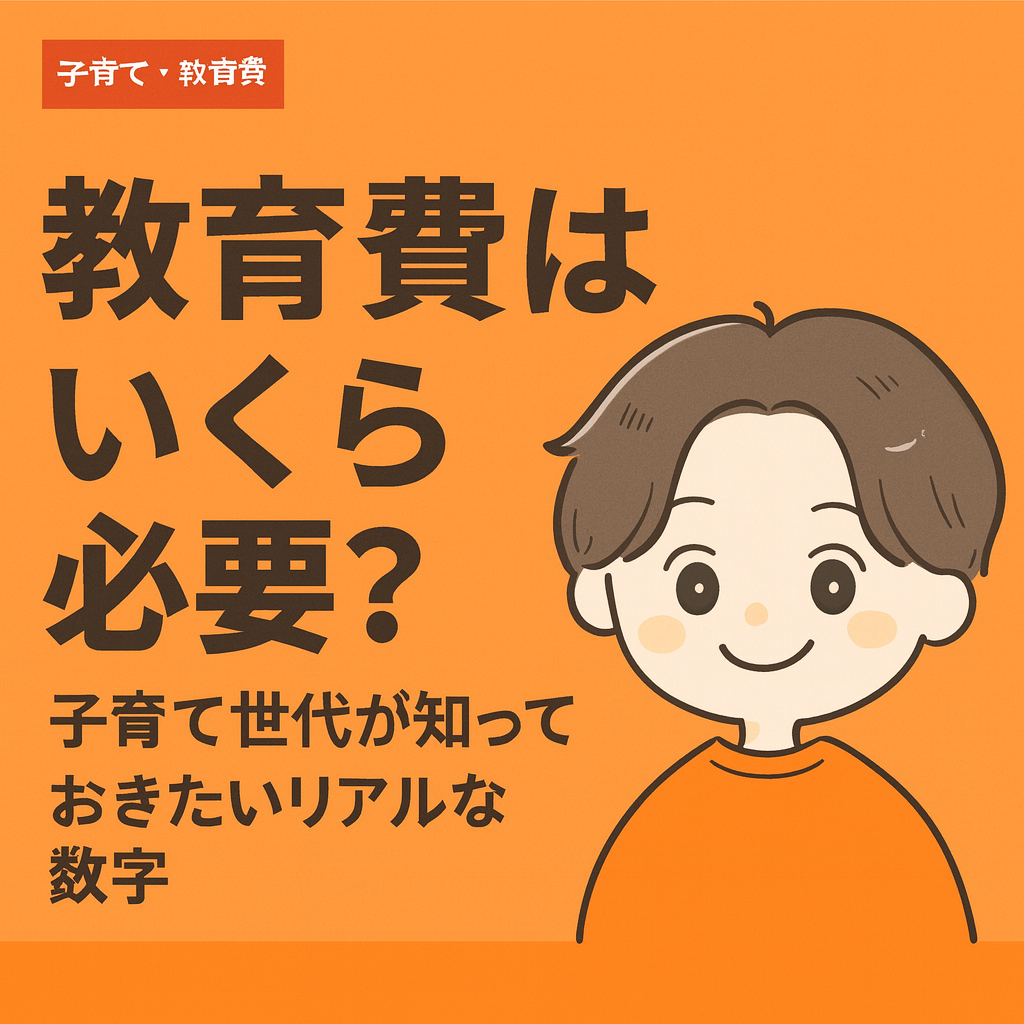
教育費はいくら必要?子育て世代が知るべきお金のリアル
教育費はどれくらい必要?公立・私立の違いや大学進学にかかる費用の目安を解説。児童手当やNISAを活用した効率的な準備法も紹介します。
子どもの将来資金は“自動積立”で先取り貯金!親がラクに続けられる投資の仕組み ↓

子供の教育資金は積立で安心!児童手当を自動で投資するメリット
児童手当を貯金をせず、自動積立で教育資金へ。先取り貯金感覚でNISAや投資信託に回すメリットを、子育て世代の実体験を交えて解説します。
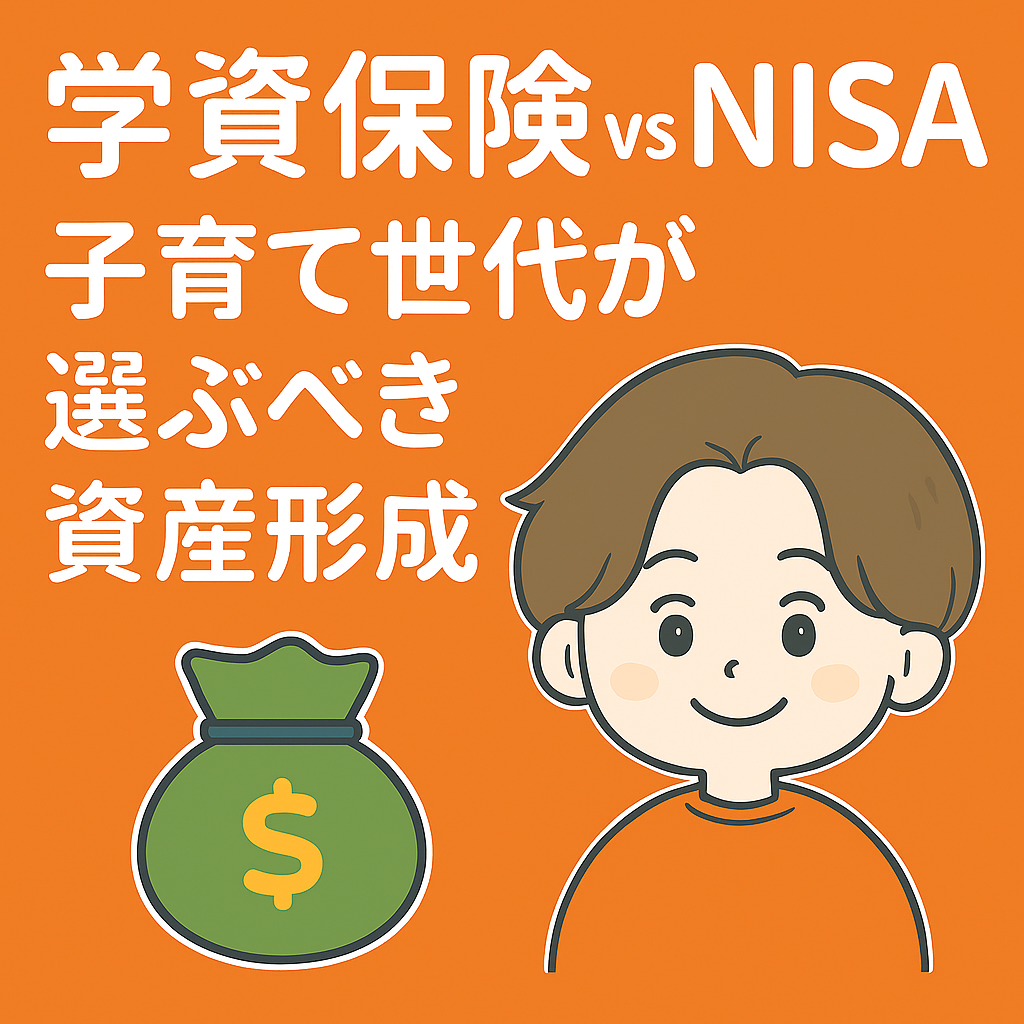


コメント